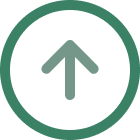近畿大学に受かるには?合格のための戦略3選
「近畿大学に受かるには、どれくらいの点数が必要?」「偏差値50台でも合格できる?」という不安を感じている方もいるでしょう。特に模試でD判定やE判定が出てしまった受験生にとっては、「本当に間に合うのか」「どんな戦略で勉強すべきか」などが大きな悩みです。
この記事では、公募推薦・一般入試・共通テスト利用など、近畿大学の入試方式ごとの違いや、偏差値50〜60の受験生が逆転合格を目指すための戦略を3つに絞って紹介します。英語・数学・国語の対策法から、スケジュールの立て方、過去問の使い方まで、塾に通っていない人でも実践できる勉強法を解説します。
限られた時間の中で効率よく「合格ライン」を超えるために、ぜひ参考にしてください。
近畿大学に受かるには?3つの合格戦略
「近畿大学に合格したいけれど、どう勉強すればいいのか分からない」という悩みを抱える受験生は多いでしょう。ここでは、合格を目指すための「戦略」を3つに絞って紹介します。偏差値50台・塾なしでも実践できる内容ばかりなので、自分に合った戦い方を見つけてください。
戦略①入試方式を見極める
近畿大学の入試には、大きく分けて「公募推薦」「一般入試」「共通テスト利用方式」「共通テスト併用方式」の4つの出願方式があります。それぞれ出題形式や配点が異なるため、まずは自分にとって有利な方式を選ぶことが大前提です。
たとえば、公募推薦は評定による足切りがなく、筆記試験の点数だけで勝負できる「実力型」の試験です。共通テスト利用入試は共通テストの結果だけで合否が出るため、国公立対策と並行できるところがメリットです。
志望学部や自分の得意科目、模試の結果をもとに、複数の方式を比較し、「合格率が高くなる出願戦略」を立てましょう。
公募推薦・一般入試・共通テスト利用・共通テスト併用の違い
公募推薦は11月に実施される試験です。多くの学部において、英語・国語・数学・理科のうちの2科目100点ずつ、合計200点と調査書の内容を総合して合否がでます。選択できる科目は学部によってある程度指定があり、英語は多くの学部で必須です。
「推薦」と名はついていますが、評定の条件がない点が特徴です。一般入試よりも倍率は高い傾向ですが、少ない科目数で早期合格を狙いたい人には向いています。
一般入試には前期A日程と前期B日程、後期日程があり、前期は1月末〜2月実施、後期は3月頭に実施されます。多くの学部において、英語・国語・数学・理科・社会のうちの3科目100点ずつ、合計300点で採点されます。学部によって選択できる科目は異なります。
最も王道の入試形式であり、推薦と比べると倍率が低く合格者数も多い点が特徴です。こだわりがない場合は、この試験方式で合格を目指すことが基本となります。
共通テスト利用方式は国公立対策と併用でき、共通テストの結果だけで判定される試験です。前期・中期・後期と3回のタイミングで実施されます。実質的な負担が少なく、国公立大学を本命としている学生が滑り止めで受ける際に向いています。ただし、合格には高い得点率が必要です。
共通テスト併用方式は、共通テストの結果と一般入試の試験結果を組み合わせて合否を判定する試験です。それぞれの試験での高得点科目同士の総合点で合否判定されるため、得意な科目がある人に向いています。
スタンダード方式・高得点科目重視方式・独自方式の違い
近畿大学の入試には、入試形式や学部ごとに、さらにスタンダード方式・高得点科目重視方式・独自方式別という選択肢が存在します。
「スタンダード方式」は最も王道な受験方式で、推薦であれば2科目、一般であれば3科目でバランスよく判断されます。全教科100点の配点であり、満遍なく点数が取れる人に向いています。
「高得点科目重視方式」は最も高得点の科目を2倍に換算したうえで、他の科目の点数と合算して合否を判定する試験です。ただし、一般入試の後期では、高得点の2科目のみで判定される形式に変わります。いずれにせよ、得意科目が偏っている人に有利な方式です。
また、一部の学部では「独自方式」が実施されています。たとえば、「理科重視方式」では理科の点数が2倍になり、「国際学部独自方式」では英語1科目で合否が判定されます。志望学部の独自方式で取り上げられている科目が自分の得意科目であれば、ぜひ利用したい方式といえるでしょう。
戦略②科目別の優先順位をつける
すべての科目に満遍なく取り組む時間がない場合、まずは「優先順位をつける」ことが重要です。
どの学部でも「英語」は必須であることが多いため、最も力を入れるべき科目といえます。その後は、残りの科目のうち得意なものを伸ばし、他科目は「最低限の得点確保」にとどめるのが効率的です。すべてを完璧にするのではなく、「合格点を超えるために必要な点数」を科目ごとに見極め、学習にメリハリをつけましょう。
以下、各科目の目標や優先順位と取り組み方を紹介します。
英語は「7割死守」を目指す
英語は近畿大学のほとんどの学部で必須であり、合格に直結する最重要科目です。長文読解・語彙・文法と多面的に出題されるため、読解スピードと正確さを両立させる必要があります。
7割(70点)を安定して取れるよう、「長文慣れ」「語彙力強化」「選択肢パターンの把握」を意識して演習を重ねましょう。何から始めれば良いかわからない時は、単語帳と文法書の反復をしつつ、赤本+予想問題での実戦演習をおすすめします。
英語の勉強法について知りたい方は以下を参考にしてください。
数学・国語は「使う方のみ」着手する
数学と国語は多くの学部で選択式です。両方とも選択しなくてもいい場合は、使う方のみ取り組みましょう。
数学は典型問題の演習と計算力がポイントです。チャート式や基礎問題集で「頻出パターン」を繰り返してください。
国語は現代文の論理的読解力が欠かせません。設問パターンに慣れることで得点率が上がるため、問題演習を通して読解スピードと設問処理力を鍛えましょう。古文に関しては、単語帳で単語力を鍛えつつ、短めの文章問題で読解力を上げることが重要です。
理科・社会は志望学部次第で調整する
理科や社会は、選択できる学部や入試方式が限定されています。自分が受験する予定の学部や方式で必要な場合のみ取り組みましょう。
生物や社会などの暗記科目は、短期間でも点数を伸ばしやすい反面、後回しにしすぎると間に合いません。夏以降は少しずつ取り組みましょう。物理や化学などは計算の知識も問われます。苦手な場合は基本的な問題集を1〜2周してから過去問演習に臨みましょう。
戦略③問題形式に慣れる&過去問を活用する
近畿大学の入試はマーク式で、選択肢の絞り込みスピードと正確さが問われます。つまり「知識」だけでなく「形式慣れ」も重要です。
まず取り組むべきは、過去問(赤本)での演習です。3〜5年分を解いて「出題パターン」「時間配分」「ミスの傾向」を洗い出しましょう。加えて、近大に特化した予想問題を活用すれば、まだ出たことのない形式にも柔軟に対応できます。予想問題は「赤本ではカバーできない最新傾向」や「初見対策」にも役立ちます。
演習は「本番と同じ形式・時間」が鉄則。模試の判定に一喜一憂せず、本番を想定した実戦演習で得点力を養うことが、合格の決め手になります。
近大合格に向けたスケジュールの立て方
「受験勉強、何から手をつければいいのか分からない」「残り時間で本当に間に合うのか不安」という受験生のために、ここでは近畿大学に合格するための現実的な学習スケジュールの立て方を紹介します。志望学部の合格点から逆算し、今やるべきことを明確にしていきましょう。
最初は目標点から逆算する
近畿大学の一般入試や公募推薦において、多くの学部で「6〜7割」前後が合格ラインです。まずはこの点数を基準に、科目ごとの目標点を設定しましょう。例えば、英語で70点、数学で60点、国語で60点を目指すように配分すると、全体で約190点(合計200点満点)に到達します。
次に、自分の現在の得点力(模試や学校のテスト)との差を把握し、どの科目にどれくらいの時間をかけるべきかを可視化します。優先順位の高い英語には毎日1.5〜2時間、他教科は交互に1時間ずつ、合計1日3〜5時間の勉強で、無理なく合格点に近づくことができます。
月別・週別の「やるべきこと」を決める
長期計画を立てる際は、「今月は何を仕上げるか」を最初に決め、その内容を1週間ごとのタスクに分割すると行動しやすくなります。
たとえば7月なら「英語の文法・語彙を一通り終える」「数学の基礎問題をチャート式で固める」、8月は「英語長文を10本読む」「国語の過去問を解き始める」など、月単位でテーマを決めましょう。その後、週ごとに「月〜水で文法、木・金で長文、土日は過去問」というように分けると、集中力も維持しやすくなります。
手帳やアプリで予定を「見える化」し、週末ごとに進捗を振り返るのも効果的です。
時間がない人の「最低限の対策セット」
直前期であっても「最低限これだけはやってほしい」という対策を以下に紹介します。
【英語】
・『ターゲット1900』などの単語帳で語彙力を強化
・薄めの文法問題集1冊を1−2周
・長文を1日1−2題(赤本 or 予想問題)
【数学】
・『白チャート』『基礎問題精講』で頻出パターンを対策
・間違えた問題を必ず解き直す
【国語】
・評論・説明文の現代文問題を1日1題演習
・古文は単語を覚える
時間がない人ほど「広く浅く」ではなく「狭く深く」が求められます。出題傾向やレベルに合った教材を1冊ずつやり込むようにしましょう。
まとめ
近畿大学に合格するには、「何となく勉強する」のではなく、合格ラインから逆算した戦略的な対策が不可欠です。入試方式の見極め、英語を軸にした科目の優先順位の決定、そしてマーク式対策に特化した演習の繰り返し、これらを地道に積み重ねることが、合格への最短ルートです。
まずは志望学部の配点や出題形式を把握し、自分に必要な「やるべきこと」を明確にしましょう。
よくある質問(Q&A)
「偏差値が足りない」「対策法が分からない」といった不安は、誰にでもあるものです。ここでは、近大受験生からよく聞かれる疑問にコンパクトにお答えします。
偏差値50台でも受かる?
はい、可能です。近畿大学の入試は「実力勝負」。偏差値は目安に過ぎず、試験本番で7割を取れるかどうかが合否を左右します。得意科目を武器に逆転も十分可能です。
赤本だけで対策は足りる?
赤本(過去問)は必須ですが、それだけでは不十分です。予想問題や参考書で演習量を補い、スピードと精度を鍛えることが重要です。赤本+1冊の問題集で基礎を固めましょう。
英語が苦手だけど克服できる?
できます。語彙・構文・長文の3点に絞って重点対策をしましょう。短文整序や長文読解など、形式に慣れることで得点が安定しやすくなります。音読もおすすめです。
模試でE判定でも出願していい?
はい、模試の判定はあくまで参考です。過去問や予想問題で得点力を高めれば、E判定からでも合格は狙えます。本番で点が取れるような“形式慣れ”と“戦略”が大切です。
近大合格を本気で目指すあなたへ
近畿大学に本気で受かりたいなら、赤本だけに頼るのは危険です。実際の入試では「時間内に正確に解く力」や「出題形式への慣れ」が問われ、独学だけでは対応が難しいポイントも存在します。
近大合格を本気で目指す受験生のために、「近大入試ゼミ」では近大に完全特化したマーク式予想問題を毎週配信しています。英語・数学・国語に対応し、スマホ1つでも対策が可能です。月額1,980円から始められ、塾に通っていなくても・時間がなくても逆転合格を狙えます。上位プランでは学習相談・スケジュール設計もサポート。「今、何をすべきか」から一緒に決められるから安心です。
また、現在LINE登録で【無料の傾向と対策資料】もプレゼント中です。興味がある方はぜひLINEの友だち登録から!
\ 近大合格へ最速アプローチ /
近大入試対策ゼミ